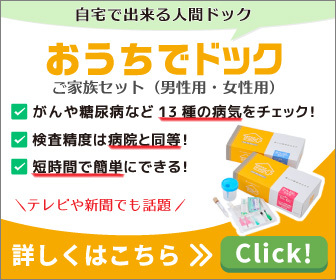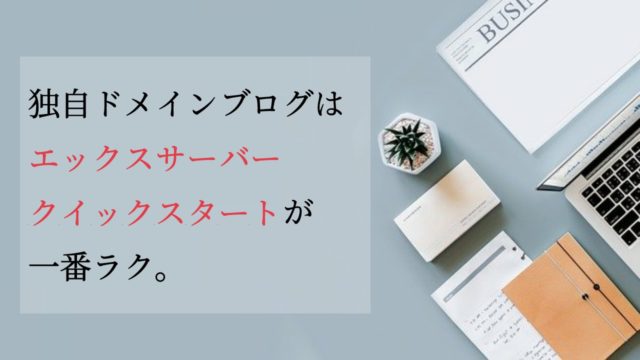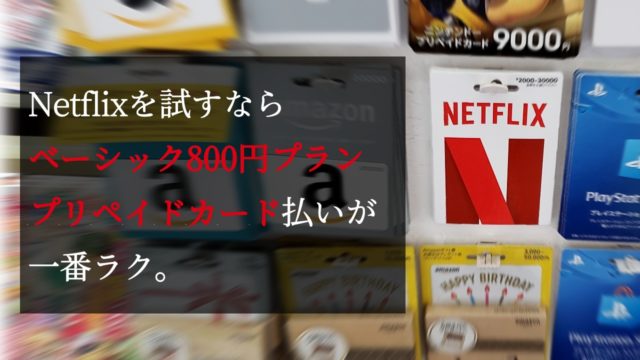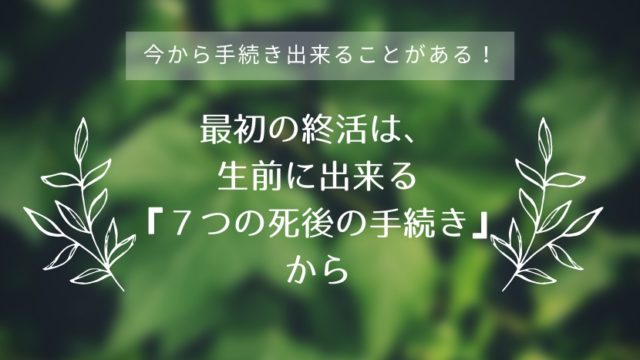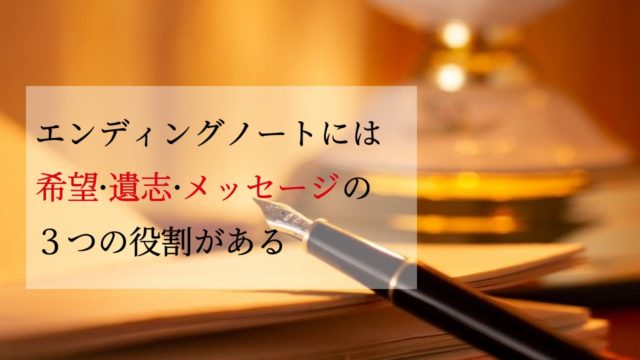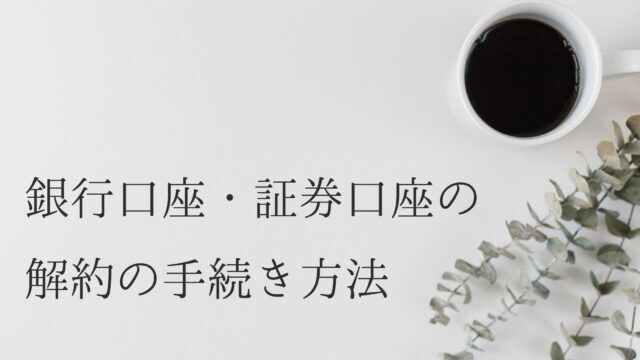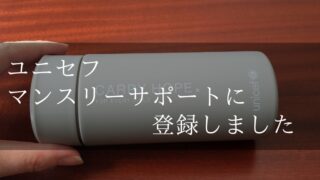健康診断や人間ドックの結果の血圧、血糖、脂質…40代は気になるところです。
そんな時に思いがけず、病気が見つかることがあります。
もしそれが「がん」だったら。
いまや2人に1人が癌(がん)にかかっているデータもあり、とても身近な病気です。
以前は不治のイメージでしたが、現在は10年生存率が56.3%という結果(国立がんセンター調べ)が出ています。
これからは、がん=慢性疾患と捉えて治療をしながら生きるのが当たり前の時代。
「いかにガンと共に生きるべきか」を考えていきます。
自分に最適な治療とは

セカンドオピニオンの活用
病院で告知 → 治療法の提案→ 治療開始
ある日、検診などで思いがけなく腫瘍が発見される。
あるいは体調不良で受診して腫瘍が見つかり、告知されて治療が始まる。
多くの人にとって、これが一般的な流れだと言われます。
思いがけない展開に慌て、とにかく一刻も早く治療を!と思ってしまうのですが、ここに加えたいのがセカンドオピニオンの制度です。
セカンドオピニオンとは:
患者が納得のいく治療法を選択できるように、違う医療機関の医師に「第2の意見」を求めること
セカンドオピニオンは、担当医を替えたり、転院したりすることではありません。最
初の担当医(ファーストオピニオン)を基本にしながら、ほかの医師に別角度から現在の治療を検討してもらうという考え方です。
その上で別の治療法が提案された場合には、選択の幅が広がって、より納得して治療に臨むことができます。
中には、担当医に遠慮してセカンドオピニオンの事を言い出せない人も、実は多いらしいのです。
確かに、担当医を信用していないように思われたりしないか、気分を害されないかと思う気持ちもわかります。
しかし、自分のデータは自分個人のものであり、何より自分の命のことです。遠慮している場合ではありません。
より良い治療を受けるための当たり前の医療行為ですので、安心してアクションを起こしてください。
「標準治療」は最善の治療
また治療は、一般的に推奨される標準治療=最善の治療であることを念頭に置いておきましょう。
決して、最新治療が最高なのでも、先進治療が最高なのでもありません。
そのような治療には臨床実験のデータが少なかったり、副作用が大きいなどリスクが多いのも事実です。
改正医療法では2018年6月から、未承認の医薬品による治療の広告や、ネット上で虚偽や誇大な表現の広告を出すことを禁止しました。
現実にそれだけ被害が多いということですね。
・標準治療を大切に考える
・セカンドオピニオンでプラスの方法を探す
お金の問題
生きていくにはお金がかかる。ましてや治療をしていくには、きれいごとではなくお金は大事です。
治療をする上で支えとなるお金の制度は3つあります。

1.健康保険(公的医療保険)
ここでは公的医療保険の事を指します。加入者およびその家族が医療を受ける際に、その医療費の一部を公的機関などが負担するという制度で、日本ではすべての国民が加入しています。
基本は、健康保険で医療費を賄っていくことになりますが、ガンの治療は手術や投薬など自己負担額も高額になってきます。それをカバーするのが高額療養費制度です。
高額療養尾費制度とは:
医療費の自己負担額が高額になった場合、保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる制度
2.障害年金
ガンになると体や心に障害を持つこともあります。そんな時に受けられる制度として障害年金があります。制度自体が知られていないことも多く手続きの煩雑さから敬遠されがちですが、ぜひ活用したいものの一つです。
障害年金とは:
障害や病気によって生活に支障が出た場合に受け取ることができる年金
障害年金の認定基準(出典:日本年金機構)
| 1級 | 身体機能の障害により日常生活が不能な場合 |
|---|---|
| 2級 | 身体機能の障害により日常生活が著しい制限を受ける場合 |
| 3級 | 身体機能の障害により労働が制限を受ける場合 |
程度によって支給額が違います。若い世代でも支給され、働きながら受け取ることができる可能性もあるので条件を満たしているかなど、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で相談することが出来ます。
3.医療保険(民間医療保険)
ここでは民間の医療保険を指します。病気やケガで治療が必要になった場合に備えて加入し、加入者がお金(健康保険料)を出し合って運営する助け合いの仕組みです。
公的健康保険を利用しても、例えば入院時の食事代などや、先進医療保険などの費用は賄いきることが出来ません。また退院後も、自宅の食事療法や通院費などお金はかかるといいます。そんな時に備えて、民間のガン保険などに入る人も多いようです。
仕事の問題
ガンの治療入院を経て自宅療養に切り替わり、日常生活ができるようになると次に考えるのは、やはり「仕事の復帰」のことではないでしょうか。
治療を理由に退職された方は復帰するにあたり求職から始めるわけで不安があるでしょうし、求職中の方も悩んでしまうことがあるでしょう。
そんな時に全国47のハローワークに設置されている長期療養者の就労支援窓口で、相談を受けてくれるのです。

<利用者の悩みや不安>
- ガンを患ったが求人があるか
- 通院の必要があるが働きたい
- 症状や体力に合った仕事をみつけたい
- しばらくぶりの復帰に不安を感じる
- 仕事復帰に際してスキル不足を感じる
- 就活で病気のことを話すべきか悩んでいる
<窓口での対応例>
- 専門の就職支援員がマンツーマンで担当
- 病状や通院に配慮した求人を紹介
- 不安解消の相談に応じる
- 応募書類の作成や面接へのアドバイス
- 就活セミナーなどの紹介
相談者は一つの拠点で年間300人ほどいるそうですが、130人ほどが就職に繋がる成果が出ています。
また地域産業保健総合支援センターの両立支援促進員に、患者と企業の間に立って意見や希望の橋渡しをしてもらうサポートもあります。公的機関なので、安心して相談してみましょう。
まとめとして
今回は身近な病ということでガンを取り上げて考えてみましたが、ガンに限らず他の病気も、あるいは事故もいつ自分事になるかわかりません。
今できるのは、まずは知ること。
どんなことに困り、どんなことが必要になるのか。
そのうえでどんな支援を受けることが出来、どんな準備や備えが出来るのかわかれば不安の解消に繋がります。

①治療の事では、治療法を考える時にセカンドオピニオンという制度を上手に活用するとよいということ。
②費用の面では、健康保険や障害年金、医療保険を組み合わせる方法があるということ。特に保険は健康な時に加入しておかないと、いざという時に使えないので前準備が必要。
③仕事の問題は、様々な支援制度が準備されている。
最も重要だと感じたのは、いかに仕事と治療の両立させるか。
治療が始まると、会社に迷惑をかけるからと離職してしまう人が多いようです。
確かに入院の間は完全に休まなければならないし、体の容態を第一に考えてしまうので仕事復帰のことなど考えられないのは当然かもしれません。
しかし治療によって徐々に日常生活も元に戻り、出来ることも徐々に増えてくるので、仕事を辞めないのが理想的な形です。
退職せずに休職制度や時短制度を利用したり、あるいは障害が出てきた場合には障害者雇用の枠を検討してもらう方法もあります。
もう一度、いま何を一番大切にすべきか優先順位をつけながら普段の生活を長く続けること。かけるお金は減ったとしても、質の上がった豊かな時間を過ごすことが人生の彩りになることもあるのかもしれません。
忙しい人為に、今は自宅で出来る人間ドックキットもあります。便利ですね!
転ばぬ先の杖としてぜひ利用してみて下さい。